亚娱体育(中国)有限公司官网位于经济发达的长江三角洲的江苏名镇——享有“剪折机床之乡”的海安李堡镇。
公司专业生产“海力拓”牌系列的剪板机、折弯机、卷板机、开卷校平剪切生产线等产品,广泛应用于:轻工、航空、船舶、冶金、仪表、电器、不锈钢制品、建筑及装潢等行业;产品畅销全国,远销欧美、东南亚、中东等国家和地区。
公司拥有多名剪、折、卷研发专家,雄厚的技术力量和先进的加工设备;生产检测设备齐全;研制开发的产品质量位居同行前列...
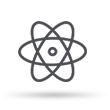
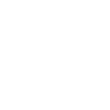


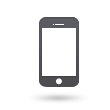
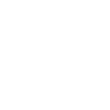
地址: 江苏省海安县李堡工业集中区(人民路) 电话:0513-88289668 传真:0513-88289819 手机:18751385222
Copyright © 2016 版权所有:亚娱体育(中国)有限公司官网 苏ICP备10091226号-1 技术支持:HUOSU